牛久市/神谷小学校
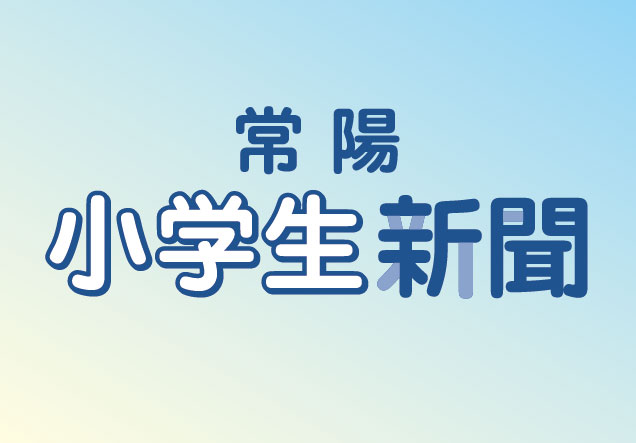
自分の身は自分で守ることを学ぶ 竜巻避難訓練や防災学習
牛久市立神谷小学校で、2月19日(水)に竜巻(たつまき)を想定した避難(ひなん)訓練が行われ、どこでも起こりうる竜巻のおそろしさを知り、自分の身は自分で守れるように避難方法を学んだ。また同日には6年生の親子防災学習も実施(じっし)。災害時に役立つ救助方法や知識を学び、自分たちに何ができるかを考えるきっかけとなった。
竜巻から身を守るダンゴムシのポーズ
竜巻避難訓練に先がけ、5年生は社会科の「日本の自然災害」の学習で竜巻について調べた。竜巻のおそろしさや発生の兆候(ちょうこう)、竜巻が発生したらどうしたらよいかなどを調べたり、学校内のどこが避難に適しているか校内を歩いて探し回ったりした。その成果を生かし、訓練の前には全校児童に向けて竜巻がきたときの避難方法である「窓から離れてダンゴムシのポーズ」を伝えた。本番では、子どもたちは放送が入ると落ち着いて素早く窓からはなれ、かべ側の机をどかして避難スペースを確保。壁に頭を向けて両手で頭と首を守る「ダンゴムシのポーズ」で安全が確認できるまで待機した。そしてふり返りでは、地震(じしん)や火災とちがって、竜巻が起きたときは外に出ずに建物内で待機することなどを確認した。
体験から学ぶ人命救助と防災学習
6年生の親子学習会は、「地域防災と人命救助」をテーマに行われた。グループに分かれ、AEDの使い方や心臓マッサージの方法を教えてもらい、人形を使って実際に体験しながら学んだ。またロープワークではほどけないロープの結び方を教えてもらい、子どもたちは慣れない結び方に苦労しつつ真けんに取り組んだ。
さらに自然災害が起きたときに役立つ救助方法や知識も学び、救命ボートや避難所で使う簡易トイレなどの実物を見学した。災害を自分事としてとらえることができた子どもたちからは「災害が起きた時に生かせる学習ができた」という感想が聞かれた。
地域の一員として自分たちができること
防災学習会には6年生の保護者のほか、地域の人の参加もあり、地域や家庭とともに学ぶよい機会になった。防災学習会は毎年行っていて、一昨年は学校が避難所になったことを想定し、体育館に段ボールベッドを設営するなど、避難所設営について学んだ。日ごろから地域とのつながりが深く、地域の人たちにお世話になっている子どもたち。自分たちも地域の一員として、災害時に何ができるかを考えられる子どもたちが育っている。


