つくば市/つくば市教育局
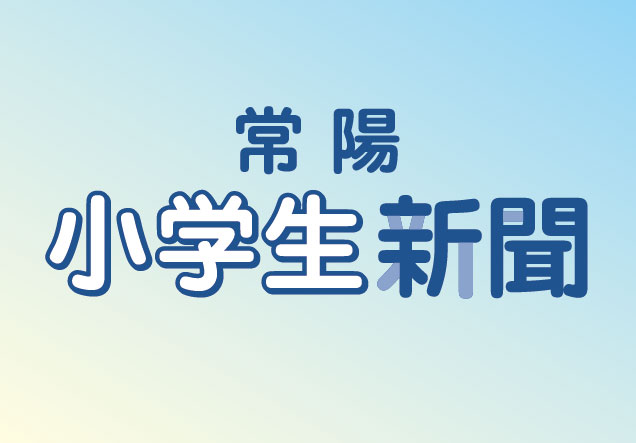
AIにヒントをもらいながら私たちが考えた「未来の公園」
つくば市では今年も夏のキッズプロジェクトが、市総合教育研究所(同市大形)で行われた。「プログラミングでドローンを動かそう」「身近な困りごとをプログラミングで解決しよう」「ALTと英語でふれあおう」など四つの講座があり、7月28日(月)の「生成AIを使ってプレゼンテーション上手になろう」では、市内の小学3〜6年生30人がいっしょになって学び合った。
グループワークでアイデアを出し合う
28日の講座は「未来の公園は、こんなふうになっていたらいいな」というテーマで、子どもたちは3〜4人ずつの班に分かれて話し合いを始めた。各班は生成AI(人工知能)から情報をもらったり、インターネットで画像を探したりして意見をまとめ、プレゼンテーション用の資料を作成した。
プレゼンテーションでは「ロボットといっしょに遊べる」「声で動くブランコがあり障がい者の人も楽しめる」「全体がクッションになっていて赤ちゃんでも安心」「1キロメートルのすごく長いすべり台がある」「グミのジェットコースターやポッキーのうんていなどおかしがたくさんある」「蛇口(じゃぐち)をひねるとジュースが出てくる」など、未来の公園の楽しいアイデアがたくさん発表された。各班のプレゼンテーションの最後には、画像生成AIが子どもたちの発表を基に作った、それぞれの未来の公園のイラストも見ることができた。
AIがくれるのは答えじゃなく意見
参加者の感想としては「AIへの質問では、期待した答えが出てくることも、意外な答えが出てくることもあった」「画像生成は思っていたのとはちがう感じがあった」「発表や自分の意見を考えるのが楽しかった。AIではできないことがあることも分かった」などの声が聞かれた。
「子どもたちはAIは何でも教えてくれると思いがちだが、実際に使ってみるとAIがくれるものは答えではなく意見であり、その判断は自分たちでしなくてはいけないことを、体験しながら分かってくれた」と、指導主事。実際に、AIの回答を子どもたちがかみくだいて理解しながら、「いいね」「ちょっとちがうね」などと評価する様子もあちこちで見られた。
理解と活用を両輪にAIと生きる未来へ
保護者の一人は「今後の子どもたちの時代には、おそらくAIの活用の仕方が今よりも数段階高度になり、AIと社会とのかかわりも変わってくるだろう。子どもたちが実際にAIにふれて親しめる、今回のような機会を増やしてほしい」と求めた。
「AIの技術進展や社会への浸透(しんとう)は予想以上に早く、情報モラルやリテラシーの問題も重要度を増している。AIを活用しながらその特ちょうやメリット・デメリットに気付いていき、やがてAIを使いこなしAIとより良く共存できる人材を育んでいきたい」と指導主事は目標を話した。

