水戸市/大野小学校
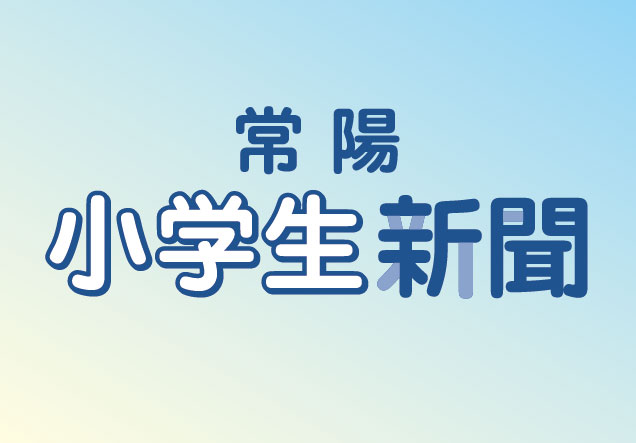
ICTを活用しながら笑顔で学べる学校づくり
水戸市立下大野小学校は、水戸市内に5校ある小規模特認校の一つで、ICT(情報通信技術)を活用した教育が特色。さらに地域に伝わる伝統芸能「大野みろくばやし」の継承(けいしょう)にも力を入れている。先端(せんたん)技術と伝統のなかで、子どもたちは笑顔の日々を過ごしている。
ICTを文ぼう具の一つとして活用
同小では、「児童が『できた』『わかった』『考えた』『やってみたい』を実感できる『笑顔の成長』を追究する」を目標に、授業や活動を通して一人ひとりが笑顔で自分の力をのばしていくことに取り組んでいる。教育の特色は、ICT活用を生かした小規模特認校であること。近くにある県立IT短大と連携(れんけい)したり、水戸市のICT支援(しえん)員のサポートを受けながらプログラミングを学び、未来に役立つ仕組みを考えたり、自分たちのプログラミングでドローンを動かすことにチャレンジしたりしている。ICTについては、「日常使い・効果優先」を合言葉に、子どもたちは授業で使う文ぼう具の一つとして活用している。
「大野みろくばやし」をずっと守り伝える
「大野みろくばやし」は、徳川光圀公が領内めぐりをした時に3体の人形を拾い、この人形をみろく人形として下大野村の役人に授けたことが始まり。以来、地域の人々は、顔が青・赤・黄色の3体のみろく人形が五穀豊穣(ごこくほうじょう)をいのり、楽しい動きでおどる「大野みろくばやし」を大切に守り続けてきた。同小では保存会の指導を受けながら5・6年生が授業の一環(いっかん)として「大野みろくばやし」を練習し、5月の運動会や、「風土記の丘ふるさとまつり」(ダイダラボウまつり)、下大野市民センター「皆コーまつり」で披露(ひろう)している。
交流や体験を通して広がる笑顔
地域との交流にも力を入れ、JAのサポートで田植えや稲(いね)かり体験をしたり、校庭の畑では、1・2年生がサツマイモ、3年生が大豆の栽培(さいばい)を行ったりしている。学校内での交流も多く、昇降(しょうこう)口を入ってすぐの「みろくホール」は休み時間に子どもたちが集う場となっている。異学年交流も盛んで、縦割り班での掃除(そうじ)や、いっしょに遊ぶ時間をつくっている。ふだんから他の学年といっしょに遊ぶなど、縦のつながりが自然にできている。「子どもたちが笑顔で学べる学校を、これからも大事にしていきたい。興味があればいつでも見学できるので、ぜひ一度見に来てほしい」と校長は話していた。


