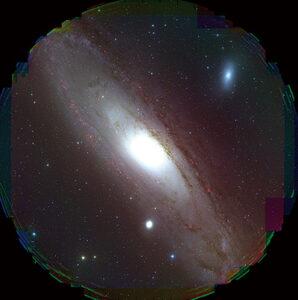つくば市/高山学園
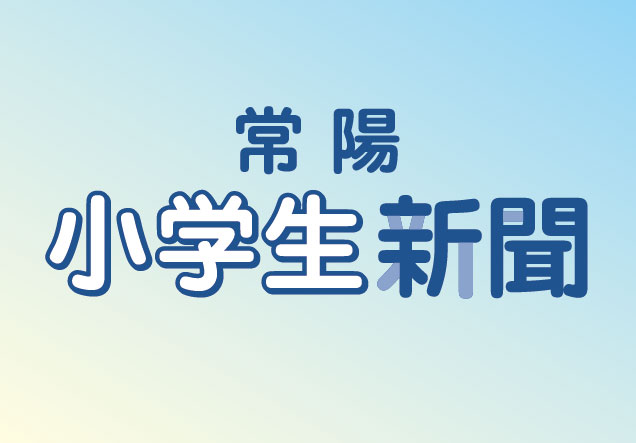
縦割り班活動による異学年交流で協働しながら人間関係を深める
つくば市立高山学園(真瀬小学校島名小学校・香取台小学校・高山中学校)の教育目標は「元気なあいさつ、深い学び、伸びる学園・学校」。真瀬小学校では小規模校の特ちょうを生かした異学年交流により、親密な人間関係が構築されている。
楽しく遊べるようルールも工夫して
真瀬小の「ませっこタイム」は縦割り班活動の時間。ロング昼休みのときに月1回ほど、班ごとに校庭・体育館・教室に分かれて、外遊びやスポーツ、ゲームなどをする。
それぞれの班がどんな遊びをするかは、半年ごとの会議のとき、6年生がみんなの意見を吸い上げながら決めている。ルールも自分たちで工夫して、例えばおにごっこでは低学年はふつうに走ってにげられるが、高学年はスキップでしかにげられないなど、だれもが楽しく遊べるよう工夫している。
「ませっこタイムは上級生にとってリーダーシップを発揮するよい機会。どうすれば班の運営がうまくいくか考え、その成果として企画(きかく)力や表現力が高まり、達成感なども感じられている」と教頭。
子どもたち同士で教え合いながら
同小では毎年、地域の農家から借りた学校の裏の畑で、サツマイモの栽培(さいばい)をしている。全校児童のほか島名幼稚園の年長園児も加わり、5月に苗(なえ)を植え、育ったイモを10月に収かくする。このときも活動のベースは縦割り班で、上級生から習った方法を下級生へと、世代をこえて伝えていく場にもなっている。
例えば苗の植え方では、サツマイモの場合は稲(いね)のように立てて植えるのではなく、横にねかせて植えた方が根つきがいい。それを低学年や園児にも分かりやすく伝えようと、上級生は頭をひねって表現を工夫する。ふり返りでは「うまく教えられて良かった」「もっと言葉を選んで上手に伝えられるようになりたい」などの気付きが得られ、自己肯定(こうてい)感や自己有用感の向上にもつながっている。
常に相手のことを思いやれるように
12月の「なかよし集会」では、おたがいを尊重し合う気持ちが育めるよう、縦割り班で話し合う。その後に行うオリエンテーリングは、集会で学んだことをさっそく実行に移す機会。上級生は下級生のペースに合わせてゆっくり歩いてあげたり、やさしく声をかけてあげたりしながら、全員が協力してクイズを解いていく。
「子どもたちには、たがいの存在を尊重し、力を合わせて学校生活を送ってほしい。楽しく有意義に学び、充実(じゅうじつ)した時間を過ごし未来を生きていく力をつけてほしい」と大久保校長は話している。