つくば市/豊里学園
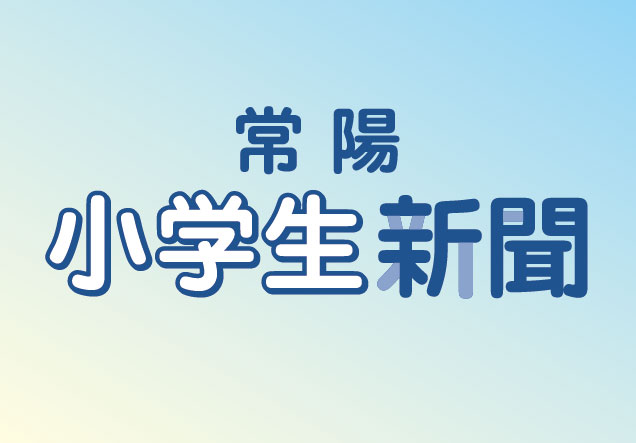
地域のフードロスを生かし探究型の学びでカレー開発
つくば市立豊里学園では「キャリア教育の視点を取り入れた探究型の学び」に力を入れており、一例として沼崎小の6年生は今年度、「もったいないカレープロジェクト」に取り組んでいる。
味やパッケージにも出したい沼崎らしさ
このプロジェクトは、地域の農産物の規格外品や売れ残り品、未利用品など、まだ食べられるのに捨てられている「もったいない食材」を活用して、沼崎小オリジナルのカレーを作り、地域課題の解決に役立てるもの。
子どもたちは食材の調査やレシピ作りから、パッケージデザイン、マーケティング、販売(はんばい)PRまで、全て自分たちで手がける。授業のわく組みはつくばスタイル科だが、フードロス問題では社会科、栄養面では家庭科、パッケージデザインでは図工や外国語科など、さまざまな教科と関連している。
プロジェクトには食品会社が協力、7月中には最初の試食会を開き、その後も改良を重ねていく予定。10月末にはレトルトパックの商品が完成し、11月の「沼崎子ども秋まつり」等での販売を目指している。
子どもたちの力で学校を作っていく
沼崎小の「なないろミーティング」は、各委員会の代表が集まる同小の話し合いの場だ。自分たちの手で学校全体を良くしようという意識で、活発な意見を交わし合っている。例えばルールメイキングの活動では、休み時間のタブレットの使い方や、グラウンドでの遊び方などを話し合った。ミーティングで決まったことは、各委員会が連携(れんけい)し主体的に実行に移していく。
同小では来年4月の創立150周年に向けて、記念イベントなどを計画中。なないろミーティングが中心となって各クラスへ呼びかけ、全児童が一丸となり取り組んでいる。
主体的に学ぶ力や表現する力を向上
同小ではロング昼休みの時間を使って、特技発表会を定期的に開いている。自分でやりたいことを何でも自由に選んで申しこみ、勇気を出してステージに上がる。
発表をみんなに見てもらうことで、いろんな感想がもらえて自信がつき、自己肯定(こうてい)感を高めることができる。友達の発表を見て学んだり、友達の意外な一面を発見したりすることは、人間関係づくりにもつながる。
「『キャリア教育の視点を取り入れた探究型の学び』からは、今の勉強が自分の将来にどうつながるかや、社会とのかかわりなどが意識でき、目標に向かってチャレンジできる子どもが育つ。人間関係形成・社会形成能力や、自己理解・自己管理能力など、幅(はば)広い教育活動を通じて多様な力を高めていきたい」と校長は話している。


